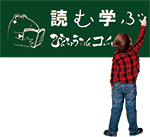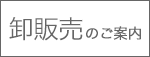未来を拓く、「有機栽培 銀河のしずく」
岩手生まれ・岩手育ち。育てるひとたちの想いがひとを繋ぐ味になりました。

プレマシャンティ®は、繋がりのなかで生まれます。
それは人であったり、自然であったり、商品であったりします。
ご紹介頂いたご縁を辿って各地を旅するうちに、その土地だからこその出会いもあります。
その土地でしか、その時期にしか出会えない味。
皆さんにご紹介したいけれど、生ものであったり、作る量が限られていたりと、私たちがお預かりするには難しい商品も決して少なくありません。
また作り手を身近に感じて初めて、より深い味わいが生まれる商品もあります。
プレマシャンティ®の開拓チームが、各地を巡り、作り手の目を見て、言葉を交わして惚れ込んだ数々を、桜のカードを添えてお届けします。
「銀河のしずく」をご存じですか?

程よい粘りと甘味。
冷めてもおいしく、深みのある味。
粒が大きく、炊飯すると程よい粘りで食べ飽きない。
「銀河」の呼び名のとおり、炊きあがりはつやつやと美しく、お米の一粒一粒がきらきらと輝くように白さ際立ちます。お米の粒も大きく、揃っています。平成27年(2015年)に県奨励品種とされて以来、栽培適地とされる岩手県中央部では、ひとめぼれやあきたこまちではなく、「銀河のしずく」を育てる農家が増えていると聞きます。
「銀河のしずく」は、約10年の歳月をかけ誕生した岩手県発の新しいお米の品種(銘柄)です。
岩手県中央部向けの「良食味米」を開発すべく、耐冷性・耐病性のある「奥羽400号」と食味に優れた「北陸208号」を使い交配が始まったのが2006年。誕生した交配種2000個体から選抜した13個体で、食味試験を重ねて「銀河のしずく」が選定されました。
地域の気候風土を考慮して生まれた「銀河のしずく」が、当該地域でより育てやすいのはもちろんなのでしょうが、育てるひとたちが「岩手のお米です」と胸を張れる品種を待ち望んでいたのも、作付面積が広がっている理由のひとつかもしれません。
岩手で生きる、岩手で育つ

「これぞ岩手のお米です」と胸を張ってご紹介できるお米を、と待ち望まれた「銀河のしずく」を育てているのは、大東町有機農産物等生産組合の皆さんです。
1998年(平成10年)に誕生した同組合の代表は小島幸喜さん。
組合を結成する3年前の1995年(平成7年)から環境保全型農業に取り組み始めた小島さんは、健康な土づくりと健康な作物づくり、更にはひとの健康とのかかわりに気づき、従来の米作りの方法から徐々に有機栽培へと移行されました。志を同じくする18人の仲間とともに組合を立ち上げ、2001年(平成13年)に有機認証を取得して以来、同組合は、仲間を増やし活動の範囲を広げながら、地域とのかかわりを深めてきました。また新しく有機農家を志すひとたちやすでに有機農業を実践しているひとたち、また有機農業に関心をもつひとびとを対象に、講演会や研修会、視察の受け入れなどにも尽力しています。さらに地域の子どもたちを対象に、有機水田を「田んぼの学校」として開放し、カエルをはじめとした圃場に暮らす生き物の観察、田植え体験、わら細工づくりなど、四季折々の風景をともに実体験する機会を設けて、有機農業と地域とのかかわりを深めておられます。大東町有機農産物等生産組合が育てる野菜や米は、地域の学校給食にも登場し、子どもたちの活力づくりにも貢献しています。
「銀河のしずく」を炊いてみました!!食べてみました!
「美味しいお米」は、どんな米?

全国には、美味しいお米の品種が沢山あります。
また革新的な技術を駆使した究極のお米の開発や育成に取り組むひとたちも少なくありません。
毎年の恒例行事になった「米の食味ランキング」では、全国から100をはるかに超える銘柄が出品され、「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」を競いあっています。また毎年11月に開催されている国際コンクール、「米・食味分析鑑定コンクール」には、全国から数千点のお米が出品されます。出品数は回を重ねるごとに増えており、米・食味分析鑑定コンクール:国際大会 in 富士山 実行委員会によって発行された開催記念誌によると、2021年度に開催された第23回コンクールでは、4755の出品があったそうです。
コンクールで金賞を受賞するようなお米はほとんど手に入りませんし、また受賞した生産者が育てるお米もまたあっという間に売り切れます。食味で特Aにランキングされたお米もまた同じで、「美味しい」と引っ張りだこになりますし、それらは必ずしも「有機認証」栽培や「自然農法」ではありません。
有機だから美味しい、自然栽培だから美味しい?

「美味しい」は皆に共通するようだけれど、その実態は変幻自在。
ひとによって、場面によって、ころころと安定しないのもまた事実です。
私にとっての「美味しい」があなたにとっての『美味しい』と必ずしも一緒であるはずはないのに、それでも私たちは“美味しい”という言葉に惹き寄せられるのだから不思議です。
同じ銀河のしずくであれば、有機認証されていてもいなくても外見には大きな違いはありません。
違いがあっても見分けられる目をもつひとは、非常に少ないのではないかと思います。
だから私たち、プレマシャンティチームが見ているのは、いつだってつくるひとであり育てるひとです。
有機栽培や自然農法、減農薬という育て方はあくまでも入り口です。
育てるひとたちや彼らへ繋いでくれたひとたちがそれぞれ語る物語を聴き、作品を拝見し、調理し、頂き、血肉に変えて、「これだ!」と腑に落ちたときにご縁が繋がります。「これだ!」を弾きだすのは、嗅覚がとらえる「いい香り」だったり、味覚で感じる「美味しい」だったり、頂いたときに五臓六腑が感じるほっとするや元気が出る、身体になじむという感覚だったり、なんだかわからないけれど相性がいいぞという直感だったり・・・私たちの五感であり、時には第六感です。心地よいつくり手たちが生み出した、「私」になじみのよい作品たちが「プレマシャンティ」であり、プレマシャンティの「美味しい」なのかもしれません。




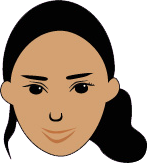




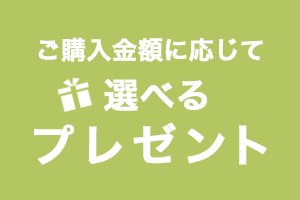
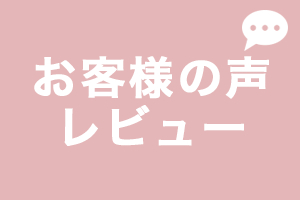
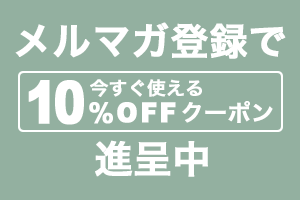

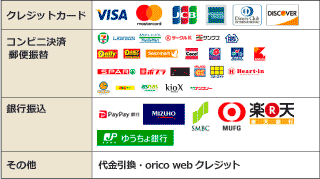











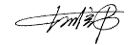











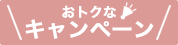




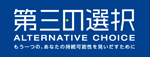





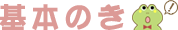
 「まるごと食べるのがいいのはわかってるんだけど……」一物全体を実践するポイントは?
「まるごと食べるのがいいのはわかってるんだけど……」一物全体を実践するポイントは?